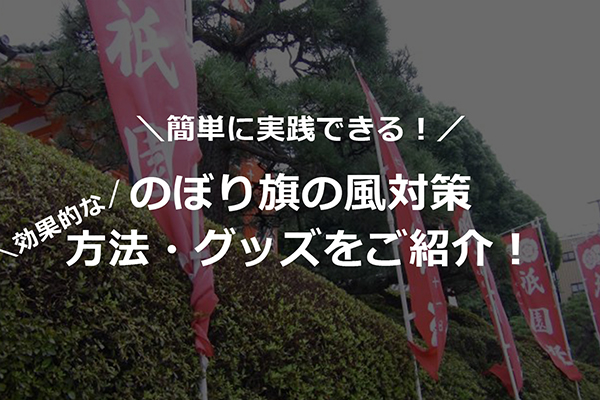
のぼり旗は店頭やイベントで使われている宣伝用の旗のことです。
街中を歩いていると、飲食店や売り出し中の物件、車のショールームなど至る所で使われているため、誰でも一度は見たことがありますよね。
私たちの生活に浸透しているのぼり旗ですが、屋外で使うときに風対策が必要なことはあまり知られていません。
店頭や道路沿いでのぼり旗を活用している方の中には、日々の強風で困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
風対策を怠ったのぼり旗は、思わぬ事故やトラブル、器具の破損に繋がる可能性があります。
のぼり旗に風対策をしっかりと行うことができれば、それらを回避できるだけでなく、宣伝効果も高まるため、一石二鳥です。
本記事では、のぼり旗に風対策が必要な理由や効果的な方法、簡単に使える風対策用のグッズなどをご紹介します。
これからのぼり旗を作ろうと思っている方はもちろんですが、すでに持っている方も参考にしてみてください。

風になびくのぼり旗
のぼり旗ってどんなもの?
冒頭でもお伝えしたように、のぼり旗は店頭やイベントで宣伝用の旗として使われています。
ほかにも神社の奉納品、スポーツ大会の応援用、道路での注意喚起など多岐にわたって活用されている旗です。
のぼり旗は「のぼり」と呼ばれており、漢字では「幟」と書きます。
ポンジやスエードなどの生地にデザインを印刷して縦長に加工し、ポールに括りつければ完成です。
のぼり旗は簡単に設置できる手軽さに加えて価格が安く、宣伝効果も高いとあって人気のある販促物ですが、屋外で使う場合には風対策が必要です。
なぜ風対策が必要なのか、具体的な理由についてご説明します。
宣伝効果が減少するため
一つ目は宣伝効果が減少するためです。
風対策をしないまま使用したのぼり旗は、巻き上がり、巻き付きを起こす可能性があります。
巻き上がりとは風によってのぼり旗がめくれ上がった状態のことを指します。一方で巻き付きとはポールにグルグルに巻き付いた状態のことです。
巻き上がりや巻き付きの状態になると、のぼり旗の内容が見えなくなり、本来の宣伝効果を発揮することはできません。
また、倒れたまま放置しておくのも見た目が良くないので、かえってマイナスのイメージを与えかねません。
のぼり旗の効果を活かすためにも、風対策が必要です。

巻き付き

巻き上がり
転倒によるケガやトラブルを防ぐため
二つ目はのぼり旗の転倒によるケガやトラブルを防ぐためです。
基本的にのぼり旗を掲げる場合は、細いポールだけで立っているため、強風の日やトラックが通り過ぎたときに転倒しやすいものといえます。
転倒したのぼり旗が道路に転がってしまうと、車の走行の妨げになり、事故やトラブルの原因になる可能性があります。
また最悪の場合は人に当たって、ケガをさせてしまうこともあるでしょう。
破損による無駄な出費を抑えるため
最後は無駄な出費を抑えるためです。
一般的なのぼり旗には、ポンジと呼ばれる薄くて軽い生地が使われているため、強風や転倒時には破れたりほつれたりしてしまいます。
また、生地を括りつけるポールも細いため、強風によって折れてしまうことも考えられます。
強風による転倒などで破損してしまっては出費が重なり、のぼり旗を設置することが経済的な負担にもなります。
風対策をすることで破損を防ぎ、無駄な出費を抑えましょう。
しっかりとした土台を使う
一つ目は、のぼり旗の設置に、しっかりとした土台を使うことです。
土台にはコンクリート製や鉄製、スチール製などありますが、おすすめは水を入れて使う注水タンクです。
コンクリート製の土台は重量があるので転倒しにくいのですが、一度設置すると移動が困難になります。
鉄製やスチール製の土台は、板状の土台の中心にある円筒にポールを差し込む形となります。このタイプは土台が非常に薄く、強風時の安定さには欠けるので屋内で使うのが良いでしょう。
注水タンクの場合、設置するときは水を入れて重くすることで安定しますが、水を抜けばとても軽くなるので簡単に移動することができます。
また、水に加えて砂を混ぜることで、さらに重くしっかりとした土台に仕上げることもできます。
土台に迷った場合は注水タンクにすると良いでしょう。

コンクリートの土台

スチールの土台

注水タンクの土台
のぼり旗に加工する
二つ目は、のぼり旗に加工することです。
まず、のぼり旗の巻き上がりを防止する棒袋加工があります。
棒袋加工とは、ポールを通す場所を筒状に縫製加工することです。
通常のぼり旗をポールに通す加工は「チチ」と呼ばれるものになりますが、棒袋加工をすることによって強風の影響を受けにくくなります。
また、のぼり旗のほつれや破れを防止するために、生地の周囲を折り返して縫製する「三巻き縫製」も効果的です。
| 加工内容 | 目的 | |
| チチ加工 | 旗のサイドにつける白い輪っか | ポールを通すため |
| 棒袋加工 | 旗のサイドを筒状に縫製加工する | ポールを通すため・巻き上がり防止 |
| 三巻き縫製 | 旗の周囲を折り返して縫製する | ほつれや破れの防止 |
| ヒートカット加工 | 熱の力で生地を溶かす | 生地をカットするため |
巻き上がり防止のグッズを使う
三つ目に、既存ののぼり旗の風対策を行う場合は、巻き上がり防止のグッズを使うと良いでしょう。
巻き上がり防止のグッズは数百円から販売されていて、楽天やAmazonで入手できるため、いずれも簡単に使うことができます。
グッズの詳細についてはこの次「簡単にできるのぼり旗の風対策グッズ3選」でお伝えします。
素材やポールを変える
四つ目は素材やポールを変えることです。
のぼり旗は、低コストなポンジ生地を使った作成が大半になります。ですが、実はポンジ生地以外でものぼり旗の作成は可能なのです。
例えば、当社ではポンジのほかに遮光スエード生地で作る場合もあります。
遮光スエードの厚みはポンジの約4倍もあるので、強度は相応に高くなるといえます。 ただし雨で水分を含むと重くなるので、のぼり旗のサイズが小さな場合に使用しましょう。
| 特徴 | 厚み | |
| ポンジ | 薄くて軽い。裏面にも印刷が透けるため両面使いができる。 | 0.14mm |
| トロピカル | ポンジよりやや厚い。裏面には多少透けるが両面使いはできない。 | 0.20mm |
| 遮光スエード | 生地の間に遮光材が入っているため両面印刷が可能。触り心地がなめらかで高級感がある。 | 0.50mm |
| ecoポンジ | ポリマーリサイクル繊維51%使用のグリーン購入法適合品。通常のポンジより透け感は劣る。 | 0.15mm |

ポンジ

遮光スエード

トロピカル

ecoポンジ
のぼり旗に使われる生地は制作会社によって取り扱うものがさまざまなので、どのような生地があるか予め確認しておきましょう。
またポールにもスチール・PE製やアルミポールなどさまざまな素材があり、折れにくいとされているのはステンレス製となります。
このように、生地とポールそれぞれの素材を見直すことも大切です。
屋内に移動させる
五つ目は、屋内に移動させることです。
風によるのぼり旗の転倒や破損を防ぐために、屋内に移動させるのも効果的です。
のぼり旗が転倒する目安としては、風速がおおよそ14m/s以上と言われています。
これは野球やテニスではボールが煽られてしまいプレーできず、自転車やバイクの運転も転倒の危険が出る状態です。
強風注意報が出てもおかしくない数値となるので、発令されたら速やかに屋内に移動させましょう。
以上が、のぼり旗の風対策におすすめの方法となります。
屋内への移動やグッズを活用した風対策であれば、すぐにでも始められるため、風に困っている方は、ぜひ試してみてください。
続いて、上記で紹介した風対策グッズを紹介します。
くるなび
ポールに取り付け、チチをフックに通すことで強風時の巻き上がりを軽減することができます。
サイズがΦ22用、Φ25用の2種類となるので、設置するポールの直径に注意しましょう。
カラマナイ
ポールに設置したのぼり旗の、最下部のチチに重しとして引っ掛けるように取り付けます。
固定するものではなく、重さによって巻き上がりを軽減することができます。
サンドチッチ
カラマナイと同じく、重さによって巻き上がりを軽減します。
最下部のチチの両側に、挟み込むようにして設置します。
風対策をして安全にのぼり旗を活用しよう!
のぼり旗になぜ風対策が必要なのか、どのような風対策があるのかをご紹介しました。
強風などの日に、風対策をせずのぼり旗を屋外に設置しておくと、思わぬトラブルや事故、破損に繋がります。
既にのぼり旗を活用しており、風対策ができていなかった方は、これを機に風対策グッズの購入や設置場所、設置方法を改めて確認してみましょう。
一方で、これからのぼり旗を作ろうと思っている方は、素材にトロピカルを使ったものや棒袋加工があるのぼり旗がおすすめです。を検討してみてください。
また、すでにのぼり旗を持っているという方は、土台を変えてみたりグッズを導入したりするのも良いですよね。
あまりの強風であれば無理に設置せず、屋内に移動させる判断も大切です。
正しい風対策をして、安全にのぼり旗を活用しましょう!
関連記事
2025.01.28
最新鋭機 VUTEk Q5r 導入レポート!
2024.08.06
【インタビュー】現代アートにおけるインクジェット印刷の可能性
2023.09.14
店頭販促とは?基本のアイテムや効果的な使い方を徹底解説!
関連記事
2025.01.28
最新鋭機 VUTEk Q5r 導入レポート!
2024.08.06
【インタビュー】現代アートにおけるインクジェット印刷の可能性
2023.09.14


